「経理担当が退職するって…どうしよう」
そんな不安を抱えていませんか?求人を出しても応募が来ない、やっと採用できたと思ったら数日で辞められてしまう、経験者を探しているのに「惜しい!」という人ばかり…。実は私も、子会社10社ほどの経理を本社でまとめて処理する中で、何度もこの壁にぶつかってきました。
ある時は総務担当が退職することになり、半年の猶予があったにも関わらず、採用した人が3人連続で数日で退職という悪夢のような事態に。採用コストだけがかさんでいく状況でした。別のケースでは、子会社の経理担当が人間関係によるトラブルによって、ある日突然退職。引き継ぎなしで別の事務員に任せることになり、仕事の品質は下がるし、後任担当者のモチベーションも急降下。募集をかけても新しい人はなかなか来ない…そんな経験をしてきました。
なぜ、経理の採用はこんなにも難しいのでしょうか?
実は、経理人材の採用難には表面的な「人手不足」だけでなく、もっと深い構造的な問題が隠れています。2040年問題による労働力不足が深刻化する中、企業は今から経理体制の強化を急いでいます。経理職の平均年収は約484万円ですが、中小企業ではこの相場に届かない給与提示も多く、大手企業との採用競争で不利な状況に。さらに学校経理、建設業経理、農業経理、小売業経理…と業種ごとに必要なスキルが異なるため、「経験豊富で能力も高いけど、うちの業種の経験がない」という惜しいケースが本当に多いんです。
私自身、10社もの経理を処理する立場だからこそ見えてきたことがあります。それは、多くの企業が「経理=採用しなければ」という思い込みに縛られているということ。でも本当は、**「そもそも社内で経理を採用し続けるべきなのか?」**という根本的な問いに向き合う必要があるんです。外部の経理代行やアウトソーシング、ツール導入で解決できる可能性があるのに、その選択肢に気づいていない企業は意外と多い。そして採用が難しいなら、経理業務の効率化・標準化で仕組みで補う方法もある。将来の人員リスクを減らすために、「あの人がいないと回らない」という属人化から脱却したいというのが、本音じゃないでしょうか。
この記事では、経理採用が難しい本当の理由を市場データと実体験をもとに深掘りします。そして、「人を採る」という発想だけでなく、経理代行やアウトソーシング、クラウド会計の活用など、会社の経理基盤を安定させるための複数の解決策を具体的にご紹介します。
最近、私のまわりにはスキルの高い経理スタッフが増えてきました。彼らは本業を持ちながら副業として経理スキルを活かしたいと考えている人たち。モチベーションが高く、提案力もある。こうした新しい働き方も含めて、これからの時代に合った経理体制の作り方をお伝えしていきます。
この記事を読めば、「経理が採用できない」という悩みから、「経理業務が安定して回る仕組み」を作る視点にシフトできるはずです。経営の数字を可視化し、会社の信用を守り、タイムリーな経営判断ができる体制を一緒に考えていきましょう。
経理の採用が難しいと言われる理由

経理の求人を出しても応募が来ない、面接まで進んでも条件が合わない…。そんな悩みを抱えている企業は本当に多いんです。でも「人が足りない」だけが理由じゃないんですよね。実は、もっと複雑な要因が絡み合っています。
人材不足という市場の現実
まず押さえておきたいのが、経理人材を取り巻く市場環境です。「売り手市場」という言葉、聞いたことありますか?これは求職者側が有利な状況のこと。つまり、経理スキルを持った人は引く手あまたで、企業側が選ばれる立場になっているということです。
なぜこんな状況になっているのか?いくつか理由があります。
人口減少と若手の会計職離れ
2040年には団塊ジュニア世代が定年退職を迎える「2040年問題」が深刻化しており、企業は今から経理体制の強化を急いでいます。要は、ベテラン経理担当者がどんどん退職していく一方で、若手が入ってこないという構造になっているんです。
私も実際に目の当たりにしたことがあります。ある子会社で20年以上勤めていたベテラン経理担当者が定年退職することになったんですが、その方は本当に優秀で何の問題も起こさず淡々と仕事をこなしていました。でも、いざ後任を探そうとしたら…全然見つからない。若い世代で経理を志望する人が圧倒的に少ないんですよね。
補足:2040年問題とは?
1971〜1974年頃に生まれた団塊ジュニア世代(約800万人)が65歳以上になり、大量退職する問題です。労働力不足が一気に深刻化すると予測されています。
簿記資格取得者の減少
もう一つのデータも見逃せません。経理職の登竜門とされる日商簿記検定。これまで累計2,900万人以上が受験してきた歴史ある資格ですが、近年は受験者数の推移が気になるところ。
簿記3級の合格率は40〜50%前後、2級は15〜30%前後で推移していますが、2級では難易度が高い回で合格率が8.6%まで落ち込んだこともあります。出題範囲の改定で難易度が上がったこともあり、「簿記2級は昔より取りにくくなった」という声もよく聞きます。
ここで不安に思う方もいるかもしれません。「じゃあ、簿記2級持っている人じゃないと採用できないの?」と。いえいえ、そんなことはありません!資格はあくまで知識の証明。実務経験や学ぶ意欲があれば、未経験からでも十分成長できます。このあたりは後ほど「教育・育成体制」のところで詳しくお話ししますね。
リモートやフリーランス志向の高まり
最近特に感じるのが、働き方の多様化です。リモートワークやフリーランス志向の高まりによって、優秀な経理人材が企業の正社員として働くことを選ばなくなっているんです。
実際、私のまわりにも本業を持ちながら副業で経理をやっている人が増えてきました。その方たちと話していて驚いたのが、「会社組織の中だけにいると視野が狭くなるから、いろんな企業の経理を見たい」という考え方。確かに理にかなってるんですよね。
ちょっと脱線しますが、これって採用する側からすると実はチャンスでもあるんです。正社員として採用できなくても、副業やフリーランスとして協力してもらえる可能性がある。後ほど「経理代行・アウトソーシング」のセクションで、この働き方の活用法をお伝えします。
経理に求められるスキルの高度化
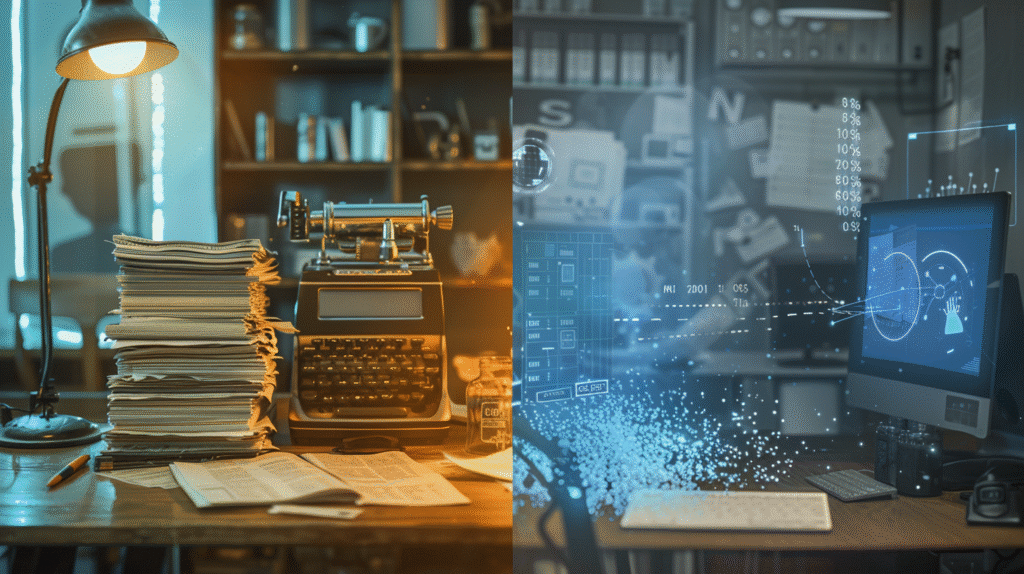
「昔の経理」と「今の経理」、実は全然違うものになってきています。単に仕訳を切って帳簿をつけるだけではなく、もっと幅広いスキルが求められるようになってきたんです。
会計ソフトやクラウド会計の知識
これ、本当に痛感したエピソードがあります。
先ほどお話ししたベテラン経理担当者の話の続きなんですが、その方が退職する時に初めて気づいたことがありました。何と、ペーパーレスが全然進んでおらず、紙運用、手書き運用、手書きによる帳簿作成などが残っていたんです!
優秀な方だっただけに、そのやり方で何の問題も起きていなかった。でも若手が入ってきた時、「なんで今どき手書き…?」と思いながらも、ベテランさんに意見することもできず、無駄とは思いながら同じ作業を続けていたそうです。
ベテラン事務員が退職してやっと紙運用を廃止し、クラウド会計を導入。一気に業務効率化が進みました。**ベテラン経理担当者が悪いわけじゃないんです。**でも、これからの時代、ITツールを使いこなせることも必要なスキルだと痛感しましたね。
フォロー:クラウド会計って何?
インターネット上で使える会計ソフトのこと。freee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなどが有名です。パソコンにソフトをインストールする必要がなく、どこからでもアクセスできるのが特徴。銀行口座やクレジットカードと連携して自動で仕訳を作ってくれる機能もあります。
ITリテラシーや業務改善の視点
ただクラウド会計を「使える」だけじゃ足りないんです。大事なのは「なぜこのツールを使うと効率的なのか」を理解し、業務改善につなげられる視点。
これも実体験なんですが、リモートワーク導入や手入力ミス削減のためにクラウド会計を導入したいという声が社内であがったことがありました。でも、「今の仕組みで何の問題も起きていない」「月額コストが発生するじゃないか」と、実務担当者からも経営者からも抵抗勢力がとても大きかったんです。
導入後も面白い(?)ことが起きました。100のうち97が効率化されたのに、残り3の非効率になった小さなところを声高に主張する人が必ずいるんですよね(笑)。トータルで97も効率的になっていることを理解できない。
ここから学んだこと:こういう人は初めから改善プロジェクトのメンバーに入れて意見をもらっておくなど、うまく巻き込んでおくことがとても大事なんだと。
大丈夫です、解決策があります!
「うちの会社、変化に抵抗する人が多くて…」という不安を感じた方もいるかもしれません。でも、適切なステップを踏めば、こうした抵抗は最小限に抑えられます。具体的な進め方は「クラウド会計・業務改善ツールの導入」のセクションで詳しく解説します。
決算対応や税務の知識など専門性の高さ
日常の経理業務はクラウド会計でかなり自動化できるようになりました。でも、月次決算や年次決算、税務申告といった専門性の高い業務は、やっぱり知識と経験が必要なんです。
しかも、業種によって必要な知識が全然違う。学校経理なら補助金の会計処理、建設業なら工事進行基準、農業なら農業簿記の特殊性、小売業なら在庫管理と原価計算、サービス業なら人件費の管理…。
私自身、10社の経理を見ている中で何度も感じたことがあります。「経歴が豊富で能力もとても高そうだが、今求めている分野の経験はない」という惜しい状況。たとえば製造業の経理経験が豊富な方でも、建設業の会計処理は未経験だったり。
現実的な解決策
あらゆる分野の経験がある「スーパー経理マン」を一人採用するのは、正直ほぼ無理です。それよりも、チームで対応する、または外注する方が現実的。それぞれの得意分野を持ったメンバーや外部パートナーと組む方が、結果的に早く確実なんです。
採用難の背景にある”本当の不安”
ここまで市場環境やスキルの話をしてきましたが、実は採用が難しいと感じる背景には、もっと深い不安が隠れているんじゃないでしょうか。
数字が見えないことへの不安
経理担当者がいないと、今月の売上がどれくらいか、利益は出ているのか、資金繰りは大丈夫かといった基本的な数字がわからなくなります。これ、経営者や管理職にとってはものすごく不安なことなんですよね。
銀行から融資の相談をされた時、「今期の業績はどうですか?」と聞かれて答えられない。税務調査が入った時、きちんと説明できる資料がない。こういった場面を想像すると、夜も眠れなくなる方もいるかもしれません。
実は、この不安の根本にあるのは「採用できないこと」ではなく、「経営の数字を見える化・管理できていないこと」なんです。
属人化リスク
これも本当によくあるケースです。ある日突然、経理担当者から「来月で退職します」と言われる。しかも引き継ぎもなく退職されてしまった…。
私も実際に経験しました。子会社で経理担当者がある日突然退職。もう一人いた事務員にとりあえず対応してもらうことになったんですが、昨日までやっていなかった業務を突然任されるわけです。
結果、どうなったか?
- 仕事の品質が下がる
- 今までやっていた自分の仕事もおろそかになる
- 本人のモチベーションも急降下
何とか私もサポートして仕事が回るところまで持っていきましたが、それでも必要な品質まではなかなか届かない。そして募集はかけているものの、新しい人もなかなか来ない…。
これが「属人化リスク」です。一人に依存して、その人がいないと業務が止まる状態。
ここが重要!
実は、採用を難しく感じる本質的な理由は、「そもそも社内の経理体制が脆弱」ということなんです。採用できないから困っているのではなく、属人化した状態のまま仕組み化できていないから、誰かが辞めた時に困る。この違い、わかりますか?
経営判断の遅れ
経理情報がタイムリーに出ないと、経営判断も遅れます。
「新しい設備投資をすべきか?」「人を増やしても大丈夫か?」「この取引先との契約を続けるべきか?」
こういった判断をする時、最新の資金繰りや利益状況がわからないと、判断が遅れるだけでなく、間違った判断をしてしまうリスクもあります。
採用の悩みの奥には、「タイムリーに経営情報を把握できない苦しさ」があるんですよね。
ここまで、経理採用が難しい理由を3つの側面から見てきました。
人材不足という市場環境、求められるスキルの高度化、そして属人化リスクや経営判断の遅れといった根本的な不安。これらが複雑に絡み合って、「採用が難しい」という状況を作り出しています。
でも安心してください。次のセクションでは、具体的にどうすれば採用がうまくいくのか、そして採用以外にどんな解決策があるのかを詳しくお伝えしていきます。
興味深いのは、最近出会った副業やフリーランスで経理をやっている人たちの視点です。会社の中だけでやっていると業務効率化に意識が向かないことが多いのに、彼らは業務改善にとても積極的なんです。「ここが非効率なのでこうした方が良い」「この方法では効率化に限界があるのでこのツールを導入した方が良い」といった提案がどんどん出てくる。
会社の中ではこういう意見はつぶされがちですが、積極的に意見を採用する経営者が伸びていくんだろうなと感じています。
さて、次は「経理採用を成功させるためのポイント」を見ていきましょう!
経理採用を成功させるためのポイント
さて、ここからが本題です。経理採用が難しい理由はわかった。じゃあ、どうすればいいの?という話ですよね。
実は、採用がうまくいかない企業の多くが、従来のやり方から抜け出せていないんです。「ハローワークに求人を出して待つ」「給与は今までと同じ水準で」「即戦力じゃないとダメ」…こういった考え方を少し変えるだけで、採用の成功率は大きく変わります。
募集条件と待遇の見直し
まず最初に見直すべきは、募集条件と待遇が今の市場に合っているかという点です。
市場の給与相場を踏まえた提示
経理職の平均年収は約509万円(令和6年賃金構造基本統計調査)。でも、これはあくまで全国平均です。実際には企業規模や地域、経験年数によって大きく変わってきます。
中小企業の経理職の年収相場は、地域差はあるものの年収350〜500万円が目安とされています。上場企業と未上場企業では約70万円の差があり、企業規模が大きいほど年収も高くなる傾向があります。
ここで「うちは中小企業だから給与は抑えたい」と思う気持ちもわかります。でも現実問題として、相場より明らかに低い給与では、応募すら集まりません。
実際、私が相談を受けたケースでこんな話がありました。新規に正社員を採用しようと思うとなかなか相場に見合った金額を捻出できない、という相談です。確かに、従業員20名規模の製造業で、経理経験者を年収400万円以上で採用しようと思うと、人件費の負担は重いですよね。
ここで考え方を変えてみませんか?
必ずしも正社員フルタイムで採用する必要はないんです。後ほど詳しくお話ししますが、オンラインで必要な作業だけを外注する、パートタイムで雇用する、といった柔軟な働き方を取り入れれば、優秀な人材を即日低コストで活用できます。
勤務形態の柔軟性(在宅・時短など)
2025年の転職市場では、リモートワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方の普及が定着しており、企業は社員が長く安心して働ける職場づくりに目を向けるようになっています。
正直に言うと、「経理は出社必須」という考え方、もう古いです。
クラウド会計を導入すれば、経理業務の多くは自宅からでもできます。むしろ、通勤時間がなくなる分、効率的に仕事ができるという声も多いんですよ。
特に、子育て中の優秀な経理経験者は、「フルタイムで毎日出社」という条件だと応募できないケースが多いんです。でも「週3日リモートOK」「時短勤務可能」という条件にするだけで、応募者層が一気に広がります。
ここで不安に思う方もいるかもしれません。「リモートだと管理できないんじゃないか」「サボるんじゃないか」と。
でも考えてみてください。経理って、数字が合っているか、期限内に処理できているかで評価できる仕事ですよね。むしろ、出社して机に座っている時間で評価するより、成果で評価する方が合理的なんです。
フォロー:リモートワークでの管理方法
クラウド会計やチャットツール(SlackやChatworkなど)を使えば、作業の進捗状況はリアルタイムで把握できます。週1回のオンラインミーティングを設定するだけで、コミュニケーション不足も解消できますよ。
採用チャネルの工夫
「ハローワークに求人を出したけど応募が来ない」という話、本当によく聞きます。もちろんハローワークも有効な手段ですが、それだけに頼っていては選択肢が狭まってしまいます。
ハローワークだけでなく専門エージェントやSNSを活用
経理職の採用には、経理に特化した転職エージェントを活用するのが効果的です。
経理に強い転職エージェントとしては、MS-Japan(管理部門・士業特化で35年の実績)、ヒュープロ(面接1回のみの求人も多数)、BEET-AGENT(経理の実務経験者に特化)などがあります。全求人の約3割が経理・財務の求人というサービスもあり、上場企業の70%以上にあたる約2,600社からの依頼実績を持つエージェントもあります。
専門エージェントの良いところは、こちらのニーズを理解した上で、適切な人材を紹介してくれること。「製造業の経理経験者がほしい」「未経験でも意欲があれば」といった細かい要望にも対応してくれます。
ただし、エージェントを使うと紹介手数料が発生します。一般的には年収の30〜35%程度。年収400万円なら120〜140万円ほどかかる計算です。
「そんな費用は出せない…」と思った方、大丈夫です。別の方法もあります。
SNSを活用した採用の可能性
実は私、SNSを使って人材を探しています。これが意外と効果的なんですよ。
なぜSNSなのか?理由はいくつかあります。
まず、面接前に候補者のことがよくわかるんです。日頃どんな発信をしているか、仕事に対してどんなことを考えているのか、改善に対する意識はどうか、得意なツールは何か。こういった情報が、SNSの投稿から見えてくるんですよね。
履歴書や職務経歴書だけではわからない、その人の価値観や仕事への姿勢が見える。これって採用する側にとってはすごく重要な情報です。
もう一つの理由。オンラインで仕事をしたいと考えている人は、SNSも活用している確率が高いんです。つまり、リモートワークOKの求人を探している優秀な人材とマッチしやすいということ。
ちょっと脱線しますが、SNSで見つけた人材って、本当にモチベーションが高い人が多いんですよ。自分から情報発信して、スキルアップに貪欲で、新しいツールにもどんどん挑戦する。そういう姿勢がSNSの投稿から伝わってくるんです。
SNSでの人材探しの始め方
X(旧Twitter)やLinkedInで「#経理」「#リモート経理」「#副業経理」などのハッシュタグを検索してみてください。意欲的に発信している経理パーソンがたくさん見つかります。DMで直接スカウトするのも一つの手です。ただし、いきなり採用の話をするのではなく、まずは投稿に反応したりコミュニケーションを取ることから始めましょう。
リファラル採用(社員紹介制度)
もう一つ、見落とされがちだけど効果的な方法がリファラル採用です。
リファラル採用とは、自社の社員から知人・友人を紹介してもらう採用手法です。マッチング精度が高く、応募から採用決定する確率が高いのが特徴で、求人広告や転職エージェントの利用料がかからないため採用コストを抑えられます。
「でもうちの社員、経理の知り合いなんていないんじゃ…」と思いますか?
実は、経理職の知り合いじゃなくてもいいんです。前職で一緒に働いていた人、大学時代の友人、異業種交流会で知り合った人…。「こういう人材を探しています」と社員に伝えれば、意外なところから紹介があったりします。
リファラル採用では紹介者に対して報酬(インセンティブ)を支払う制度を設けることが一般的で、一般的には1万〜30万円の範囲で支払われます。必ずしも採用にはつながらず、カジュアルに知人や友人を紹介できるため、縁故採用とは異なりポジティブなイメージが持たれやすい手法です。
ただし、報酬金額を高くしすぎると「友達をお金で売る」という感覚が芽生えたり、報酬欲しさに不適切な紹介をする社員が現れるリスクもあります。むしろ、会社と社長を好きな社員のみ選抜し、プロジェクト化して業務に組み込む方が効果的です。
リファラル採用を成功させるコツ
「経理経験者を紹介してください」と漠然とお願いするのではなく、「こういう業務をお願いしたい」「こういう働き方ができる」「こういう成長機会がある」と具体的に伝えること。そして、紹介してくれた社員には、結果に関わらず感謝の気持ちを伝えることが大切です。
教育・育成体制の整備
「即戦力がほしい」という気持ちはよくわかります。でも、即戦力を採用しようとすると、競争が激しいし、給与水準も上げないといけない。
だったら、未経験者や経験の浅い人を育てるという選択肢も考えてみませんか?
経理未経験者でも育成できる仕組みを準備
「え、経理未経験者なんて無理でしょ?」と思いましたか?
実は、オンラインで仕事をしたいと考えているが経験がない、でもモチベーションはとても高いしかも優秀、という人、たくさんいるんですよ。
こういう人材も、適切な育成の仕組みがあれば、十分に戦力になります。私のチームでは、未経験者でも仕事ができる方法を工夫しています。
具体的にどうしているかというと、経験豊富で優秀なメンバーがたくさんいるので、そのメンバーに意見を求めたり助けてもらいながら経験を積んでもらうという仕組みです。
例えば:
- 最初は簡単な入力作業からスタート
- わからないことがあったらすぐにチャットで質問できる環境
- 先輩の作業を見学(画面共有)してやり方を学ぶ
- 月次決算の流れを段階的に覚えていく
こうやって、チーム全体で育てるという意識を持つことで、未経験者でも3〜6ヶ月である程度の業務をこなせるようになります。そして、そうやって育った人材は、会社への愛着も強く、長く働いてくれる傾向があるんです。
大事なポイント!
未経験者を育てる時に一番重要なのは、「質問しやすい環境」を作ること。ベテラン経理担当者の中には、「これくらい自分で考えて」という姿勢の人もいますが、それだと未経験者は萎縮してしまいます。「どんな質問でもOK」「わからないことは恥ずかしいことじゃない」という文化を作ることが成功の鍵です。
マニュアル化と標準化の重要性
未経験者を育てるために必須なのが、業務のマニュアル化と標準化です。
「ベテラン経理担当者の頭の中にしかない」という状態では、誰も育てられません。
- 月次決算のチェックリスト
- 仕訳のパターン集(よくある取引の仕訳例)
- 会計ソフトの操作手順書(スクリーンショット付き)
- トラブル対処法のFAQ
こういったマニュアルを整備しておくと、未経験者の成長スピードが格段に上がります。
**そして実は、マニュアル化には副次的な効果もあります。**それは、属人化の解消です。
「あの人がいないと仕事が回らない」という状態から、「マニュアルを見れば誰でもできる」という状態に変えることで、採用のハードルも下がるんです。「即戦力じゃないとダメ」ではなく、「やる気があれば大丈夫」と言えるようになる。
マニュアル作成のコツ
いきなり完璧なマニュアルを作ろうとしなくてOKです。新しい人が入社したら、その人がつまずいたポイントをメモしておいて、それを元にマニュアルを少しずつ充実させていく。この積み重ねが、結果的に最も実用的なマニュアルになります。
決算や税務は外部サポートも活用
ここで現実的な話をしましょう。
未経験者を育てるといっても、決算や税務申告といった専門性の高い業務は、やっぱり経験が必要です。
これらの業務は、間違えると会社に大きな損害を与えるリスクもありますし、税務調査で指摘を受けることもあります。
だから、日常の経理業務は社内で対応しつつ、決算や税務申告は税理士や会計事務所に依頼するというハイブリッド型がおすすめです。
後ほど「経理代行・アウトソーシングの活用」のセクションで詳しくお話ししますが、全部を社内でやろうとしなくていいんです。得意な部分は社内で、専門的な部分は外部に。この使い分けが、中小企業の経理体制を安定させる鍵になります。
さて、ここまで「採用を成功させるためのポイント」として、待遇の見直し、採用チャネルの工夫、育成体制の整備についてお話ししてきました。
でも、もしかしたらこう思っている方もいるかもしれません。
「それでも採用できなかったらどうするの?」 「そもそも、本当に社内で経理を雇い続ける必要があるの?」
次のセクションでは、「人を採る」だけが答えではないという、もう一つの重要な視点をお伝えします。これが、実は多くの中小企業にとって最適解になるかもしれません。
「人を採る」だけが答えではない
さて、ここまで「経理採用を成功させるためのポイント」をお話ししてきましたが、実はもう一つ重要な選択肢があります。
それは、「そもそも採用しなくてもいいかもしれない」という視点です。
「え?採用しないで経理業務どうするの?」と思いましたよね。でも、よく考えてみてください。経理担当者を雇うことが目的ではなく、経理業務がきちんと回ることが本当の目的なはずです。
その目的を達成する方法は、採用だけじゃないんです。
経理代行・アウトソーシングの活用
専門性の高い外部パートナーに任せるメリット
経理アウトソーシングとは、企業の経理業務の一部または全部を外部の専門業者に委託するサービスです。
最大のメリットは、すぐに経理業務を依頼できること。採用活動をして、面接して、入社を待って、教育して…という時間が必要ありません。委託先によっては、契約から最短即日で業務を開始できることもあります。
実際、私が相談を受けたケースでこんな話がありました。新規に正社員を採用しようと思うとなかなか相場に見合った金額を捻出できない、と。
その企業には、私の事業のようなオンラインで必要な作業だけを外注するという使い方を提案しました。優秀な人材を即日低コストで活用してもらうことができ、とても喜んでもらえたんです。
具体的にどんなサービス?
私が提供している経理代行サービスを例にすると、3つのプランがあります:
- 記帳代行プラン(月6千円〜):日々の取引を記帳するだけ
- 経理代行ミニプラン(月5万円〜):記帳+ITツール導入支援+経費精算+各種レポート
- 経理代行スタンダードプラン(月15万円〜):売上・仕入管理から給与支払い、年末調整、税理士連携まで
年収400万円の経理担当者を雇うと、社会保険料込みで年間500万円以上。でも月5万円のプランなら年間60万円。しかもITツールの導入支援や業務改善の提案までついてくる。

採用リスクを回避しつつ、必要な時に必要なサービスを利用できる柔軟性
アウトソーシングの大きな魅力は、柔軟性です。
正社員を雇うと:
- 繁忙期も閑散期も同じ人件費がかかる
- 退職されたら業務が止まるリスク
- 育成に時間とコストがかかる
- 「この人に合わなかった」と思っても簡単に解雇できない
一方、アウトソーシングなら:
- 決算期だけスポットで依頼することも可能
- 担当者の退職リスクは業者側が負う
- 専門知識を持ったプロがすぐに対応
- 合わなければ契約を終了できる(縛りなし)
「でも、社内にノウハウが蓄積されないのでは?」という不安を感じた方もいるかもしれません。
確かにこれはアウトソーシングのデメリットとしてよく指摘される点です。でも、考え方を変えてみませんか?
まず、すべてを外注する必要はありません。日常の簡単な業務は社内で対応し、決算や税務申告といった専門性の高い部分だけ外注する「ハイブリッド型」という選択肢もあります。
そして実は、優秀なアウトソーシング業者は、業務の仕組み化やマニュアル作成も一緒にやってくれるんです。私のチームでも、クライアント企業の業務フローを整理して、将来的に社内で対応できるような仕組みづくりまでサポートしています。
実際の成功事例
あるIT企業の代表からこんな声をいただきました: 「非常にスピード感があり、経理だけではなくITにも詳しいためデータを渡せばスムーズに対応してくださいます。経理だけ詳しい担当者ですと、レシートの郵送を希望されたりCSVファイルの文字化けで差し戻しになったりなど、とにかく時間がかかることが多いのですが、『経理とITの二刀流』のため、煩わしいことが一切ありませんでした」これって、まさに「経理×IT」の強みなんですよね。単に経理業務を代行するだけじゃなく、データ処理やシステム化も含めてサポートできる。
費用感はどれくらい?
経理アウトソーシングの料金は、委託する業務内容や企業規模によって異なりますが、一般的な相場は:
- 税理士事務所(個人事業主・零細企業向け):月5〜20万円程度
- オンライン型の経理アウトソーシング会社:月3〜10万円程度
- センター型の経理アウトソーシング会社(大規模対応):月10〜50万円、場合によっては数百万円
正社員を雇うより高いか安いか?
年収400万円の経理担当者を雇う場合:
- 給与:約400万円
- 社会保険料(会社負担):約60万円
- 採用コスト:約50万円(エージェント利用の場合)
- 教育コスト:???
- 合計:年間500万円以上
月10万円のアウトソーシング:
- 年間120万円
単純計算で、年間380万円のコスト削減になります。しかも、採用活動の手間も、教育の時間も、退職リスクもゼロ。
注意点!
ただし、アウトソーシングすると情報漏えいのリスクもあります。機密性の高い情報を外部に提供するため、セキュリティ対策が万全か、秘密保持契約を締結するかを慎重に確認することが不可欠です。また、経理業務の大部分を外部業者に委託すると、社内に経理のノウハウが蓄積されにくくなります。将来的に自社で対応したくなった時のことも考えて、一部業務は社内に残しておく方が賢明です。
クラウド会計・業務改善ツールの導入
もう一つの重要な選択肢が、クラウド会計や業務改善ツールの導入です。
属人化を防ぎ、誰でもアクセスできる体制づくり
クラウド会計の最大のメリットは、「あの人がいないと仕事が回らない」という状態から脱却できることです。
従来の会計ソフト(パソコンにインストールするタイプ)だと:
- そのパソコンの前に座らないと作業できない
- 担当者が休むと業務が止まる
- データのバックアップを忘れたら大変なことに
クラウド会計なら:
- インターネットがあればどこからでもアクセス可能
- 複数人で同時に作業できる
- 自動でバックアップされる
- 銀行口座やクレジットカードと連携して自動仕訳
実際の効率化事例をお話ししましょう。
ある企業で、受け取った請求書データを取り込んで支払データにするシステムを導入しました。これによって:
- 紙保存が不要に:請求書を紙でファイリングする手間がゼロ
- インターネットバンキングへの入力作業が不要に:今まで一つ一つ手入力していた支払いデータが、システムから一括で取り込めるように。工数削減と同時に、入力ミスの可能性を大幅に削減
- インボイス番号の確認作業が不要に:システムが自動で調べてくれるので、登録可否などを都度確認する必要がなくなった
さらに、経費精算もシステム化しました:
- 現金の扱いを大幅に削減:盗難リスクが下がった
- 社員の生産性向上:会社に戻ってから清算書を作る必要がなくなり、外出先からスマホで申請できるように
これらの改善、すごく効率的ですよね。でも、導入する時は抵抗もあったんです。
導入時の抵抗勢力との戦い方
リモートワーク導入や手入力ミス削減など業務効率化のためにクラウド会計を導入したいという声はあったものの、「今の仕組みで何の問題も起きていない」「月額コストが発生するじゃないか」と、実務担当者からも経営者からも抵抗勢力がとても大きかったんです。クラウド会計ソフト導入後も、100効率化した中で3非効率になった小さなところを声高に主張する人は必ずいます。トータルで97も効率的になっていることを理解できない。
**解決策:**こういう人は初めから改善プロジェクトのメンバーに入れて意見をもらっておくなど、うまく巻き込んでおくことがとても大事だとわかりました。反対派を最初から仲間にしてしまうんです。
経営者や管理職も数字をリアルタイムに確認できる安心感
クラウド会計のもう一つの大きなメリットは、経営者がいつでもどこでも会社の数字を確認できること。
従来だと:
- 経理担当者に「今月の売上どう?」と聞く
- 担当者が資料を作ってくれるまで待つ
- 出張先では確認できない
クラウド会計なら:
- スマホやタブレットでリアルタイムに確認
- グラフやダッシュボードで視覚的にわかりやすい
- 「今月ヤバい」と思ったらすぐに対策を打てる
これこそが、採用難の根本にある不安を解消する鍵なんです。
覚えていますか?最初にお話しした「採用の難しさの裏側にある本当の不安」。
- 数字が見えないことへの不安
- 属人化リスク
- 経営判断の遅れ
クラウド会計とアウトソーシングを組み合わせることで、これらの不安すべてに対応できるんです。
主要なクラウド会計サービス
- freee(フリー):初心者向け、簿記の知識がなくても使いやすい
- マネーフォワードクラウド会計:中小企業向け、拡張性が高い
- 弥生会計オンライン:老舗の安心感、サポートが手厚い
私のチームでは、マネーフォワードクラウドシリーズの導入支援から運用までワンストップでサポートしています。単なる経理代行にとどまらず、御社の経理業務全体の効率化をご提案しています。

導入のハードルは高くない
「クラウド会計って難しそう…」と思っていませんか?
確かに、自分だけで導入しようとすると大変かもしれません。でも、導入支援をしてくれるサービスを使えば、初心者でも安心です。
私たちのようなサービスでは:
- 初期設定を全部代行
- 社員への操作説明
- 既存データの移行
- 使い方がわからない時のサポート
これら全部含めて、月数万円からサポートしています。
そして、ここが重要なポイント。
クラウド化を進めれば、基本的には社内でなければいけない仕事はほとんどなくなるんです。
強いて言えば現金の手渡しが必要な場合はもちろん出社が必要ですが、振込化を進めていくことでこれも減らすことができます。
今の仕組みの中で「外だしできること」と「社内じゃないといけないこと」を分けるというよりも、根本的に業務を見直して社内でなければいけない仕事を排除していくことが大切なんです。
さて、ここまで「人を採る以外の選択肢」として、経理代行・アウトソーシングとクラウド会計の活用についてお話ししてきました。
まとめると、こういうことです:
採用が難しいなら、無理に採用しなくてもいい。 ↓ 外部の専門家に任せる、ITツールで効率化する、という選択肢がある。 ↓ 結果として、採用コストも削減でき、属人化リスクも減り、経営の数字も見える化される。
「でも、どれを選べばいいの?」と思いますよね。次のセクションでは、これまでお話ししたすべての選択肢を整理して、あなたの会社に最適な解決策をご提案します。
まとめ
さて、ここまで長々とお付き合いいただき、ありがとうございました!
「経理の採用が難しい」という悩みからスタートしたこの記事ですが、最後まで読んでいただいて、少し視野が広がったんじゃないでしょうか?
改めて、この記事で一番お伝えしたかったこと。
それは、経理採用が難しい背景には、「人材不足」だけでなく「経理基盤が不安定」という経営的課題があるということです。
表面的には「応募が来ない」「即戦力が見つからない」という採用の問題に見えますが、その奥には:
- 数字が見えないことへの不安
- 属人化したままの業務体制
- 経営判断が遅れることへの焦り
- 会社の信用を守りたいという思い
こういった根本的な不安が隠れているんです。
だから、解決の方向性は「採用の工夫」と「仕組みづくり」の両輪なんです。
採用を成功させるために:
- 市場の給与相場を踏まえた待遇の見直し
- リモートや時短など柔軟な働き方の導入
- 専門エージェントやSNS、リファラル採用など多様なチャネルの活用
- 未経験者でも育成できる体制の整備
そして、採用だけにこだわらない選択肢として:
- 経理代行・アウトソーシングの活用
- クラウド会計やITツールの導入による業務効率化
- 社内と外部を組み合わせたハイブリッド型の経理体制
これらを組み合わせることで、最終的には「経営の数字が安定的に見える化される体制」を整えることがゴールなんです。
私自身、10社以上の経理を処理する中で、本当にいろんなケースを見てきました。
突然の退職、3人連続で数日で辞めてしまった採用の失敗、引き継ぎなしで業務が崩壊した現場…。でも同時に、クラウド化によって劇的に効率化できた事例や、副業人材の積極的な改善提案で業務が変わっていく様子も見てきました。
一つ確信を持って言えることがあります。
それは、「経理が回らないと会社は回らない」ということ。そして、「経理を回す方法は、採用だけじゃない」ということ。
あなたの会社に合った方法は必ずあります。正社員を雇うのか、パートを育てるのか、外注するのか、ITで効率化するのか。それとも全部を組み合わせるのか。
大切なのは、「今のやり方に固執しない」こと。
ベテラン経理担当者が長年やってきた紙運用を変えるのは勇気がいります。クラウド会計の月額コストを経営者に説明するのも大変です。でも、根本的に業務を見直して、社内でなければいけない仕事を排除していく。その先に、属人化しない、安定した経理体制があるんです。
- 会社の数字が見える
- お金の流れがコントロールできている
- タイムリーに経営判断ができる
こういう状態を作ることが、本当のゴールです。採用はあくまで手段の一つ。手段にこだわりすぎず、目的を見失わないでください。
もし、この記事を読んで「うちの会社、どうすればいいんだろう?」と悩んでいるなら、一度立ち止まって考えてみてください。
- 今の経理体制のどこが一番不安ですか?
- 社内でやるべきことと外に出せることを整理できていますか?
- ITツールの導入で解決できる部分はありませんか?
- 本当に正社員フルタイムで採用する必要がありますか?
私たちのような経理×ITのプロフェッショナルは、こういった悩みに一緒に向き合うことができます。無料相談から始めることもできますし、まずは一部業務だけ試してみることもできます。
経理の悩み、一人で抱え込まないでください。
この記事が、あなたの会社の経理体制を見直すきっかけになれば、こんなに嬉しいことはありません。
FAQ(よくある質問)
最後に、経理採用や経理代行について、よく聞かれる質問にお答えします!
Q1. 経理未経験者を採用しても大丈夫?
A. 教育体制を整えれば可能です!
日常の記帳業務や請求書処理といった定型業務は、マニュアル化と先輩社員のサポートがあれば、未経験者でも3〜6ヶ月である程度こなせるようになります。
ただし、決算業務や税務申告といった専門性の高い業務は、経験が必要です。これらの部分は税理士や会計事務所などの外部サポートを活用することをおすすめします。
大事なのは「質問しやすい環境」を作ること。「これくらい自分で考えて」という姿勢だと未経験者は萎縮してしまいます。「どんな質問でもOK」「わからないことは恥ずかしいことじゃない」という文化を作りましょう。
また、日商簿記3級の資格取得を採用条件にするか、入社後に取得してもらうようにすると、基礎知識の習得がスムーズになります。
Q2. 経理代行を利用すると社内にノウハウが残らないのでは?
A. 一部業務は外注しつつ、日常業務は社内に残す「ハイブリッド型」で解決可能です!
確かに、すべての経理業務を外注すると社内にノウハウが蓄積されにくくなります。でも、すべてを外注する必要はないんです。
おすすめのハイブリッド型:
- 日常業務(記帳、請求書処理、経費精算):社内で対応
- 月次決算の確認や分析:外部サポート
- 年次決算や税務申告:税理士・会計事務所に依頼
こうすることで、基本的な経理の流れは社内で把握しつつ、専門性の高い部分や繁忙期のサポートは外部に任せられます。
また、優秀なアウトソーシング業者は、業務の仕組み化やマニュアル作成もサポートしてくれます。将来的に自社で対応できるような体制づくりまで一緒にやってくれるところを選びましょう。
Q3. 中小企業が経理人材を採用する際の給与相場は?
A. 地域差はありますが、年収350〜500万円が目安です。
令和6年賃金構造基本統計調査によると、経理職の全国平均年収は約509万円ですが、中小企業では平均よりやや低めの水準になる傾向があります。
企業規模別の傾向:
- パート・非正規:年収300〜400万円
- 中小企業の正社員:年収350〜500万円
- 上場企業:年収450〜600万円以上
**ただし、相場を意識することが重要です。**市場相場より明らかに低い給与では、応募すら集まりません。
予算が厳しい場合は:
- パートタイムや時短勤務での採用
- 経理代行の活用(月3〜10万円程度から)
- 一部業務のみのアウトソーシング
といった選択肢も検討してみてください。正社員フルタイムで年収400万円+社会保険料で年間500万円以上かかるところを、月10万円の経理代行なら年間120万円で済みます。
経験者を確保するには相場を意識する必要がありますが、採用だけが答えではないということも、この記事でお伝えしたかったポイントです!
Q4. クラウド会計の導入は難しくないですか?
A. 導入支援サービスを使えば、初心者でも安心です!
確かに、自分だけで導入しようとすると大変かもしれません。でも、導入支援をしてくれるサービスを利用すれば:
- 初期設定を全部代行
- 既存データの移行
- 社員への操作説明
- 使い方がわからない時のサポート
これらすべて含めて、月数万円からサポートしてくれるサービスがあります。
クラウド会計導入のメリットは大きいです:
- 銀行口座やクレジットカードと連携して自動仕訳
- どこからでもアクセス可能(リモートワーク対応)
- 複数人で同時作業可能(属人化防止)
- 経営者がリアルタイムで数字を確認できる
導入時に多少の抵抗はあるかもしれませんが、改善プロジェクトのメンバーに反対派も最初から巻き込んでおくことで、スムーズに進められます。
Q5. 経理代行と税理士、何が違うの?
A. 対応できる業務範囲が違います!
税理士・会計事務所:
- 税務申告(確定申告、法人税申告など)
- 税務相談
- 記帳代行
- 決算業務
- ※税務に関する独占業務があります
経理代行会社:
- 日常の記帳業務
- 請求書処理
- 経費精算
- 給与計算
- ITツール導入支援
- 業務効率化の提案
- ※税務申告はできません
どちらを選ぶべき?
- 税務申告まで任せたい:税理士・会計事務所
- 日常業務のサポートがほしい:経理代行会社
- ITツールの導入や業務改善も一緒にやりたい:経理代行会社(特にIT×経理に強いところ)
理想は、経理代行で日常業務を効率化しつつ、税務申告は税理士に依頼するという組み合わせです。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!
経理の悩みは、会社によって千差万別です。でも、必ず解決策はあります。
この記事が、あなたの会社の経理体制を見直すきっかけになれば幸いです。一緒に、安定した経理体制を作っていきましょう!
- 経理採用が難しい背景は「人材不足」だけでなく「経理基盤が不安定」という経営的課題にある
- 解決の方向性は「採用の工夫」+「仕組みづくり」の両輪
- 最終的には「経営の数字が安定的に見える化される体制」を整えることがゴール
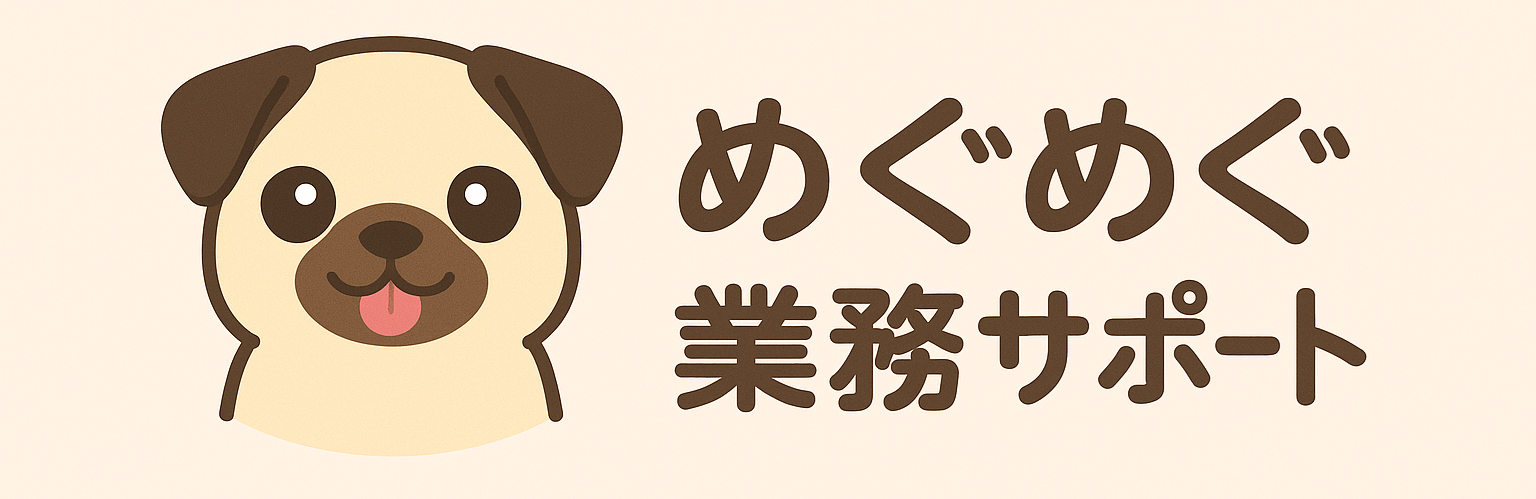
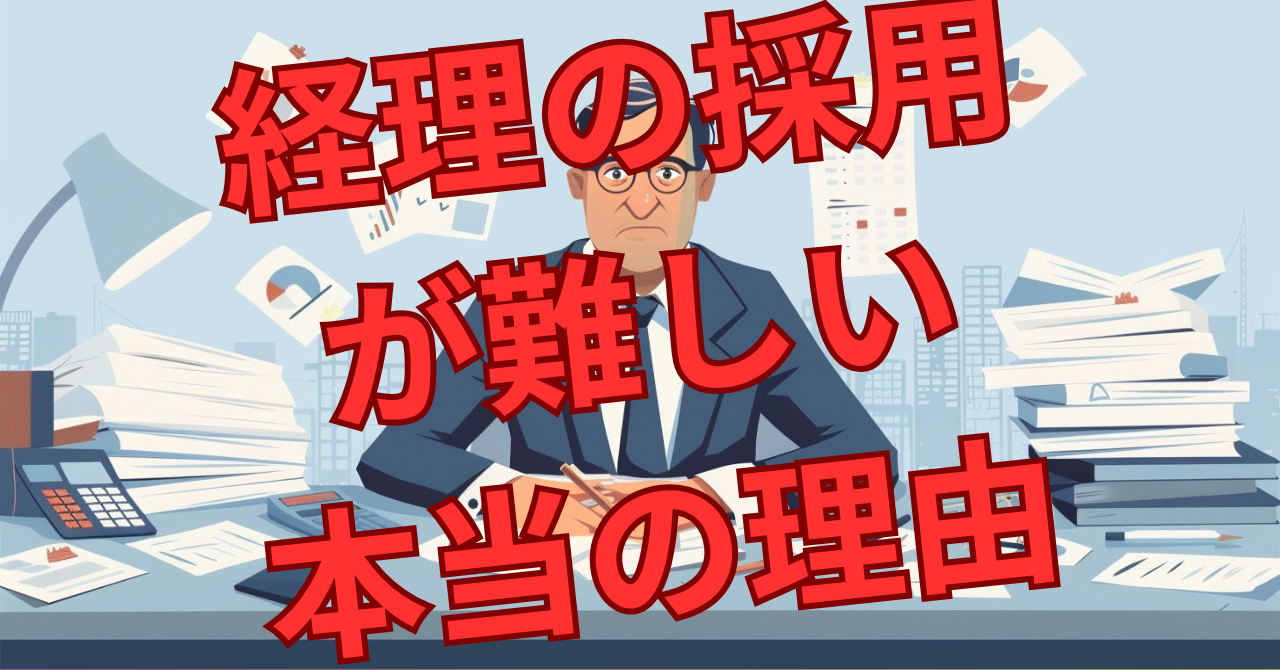
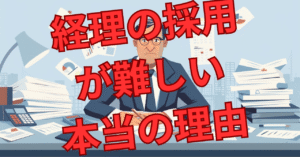
コメント